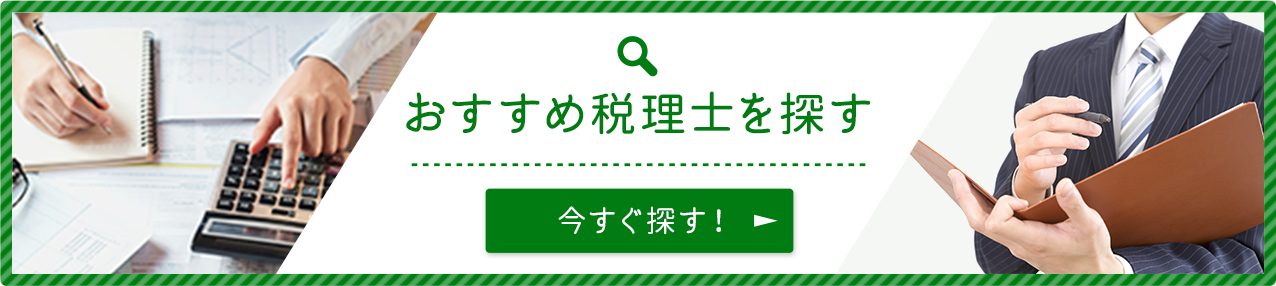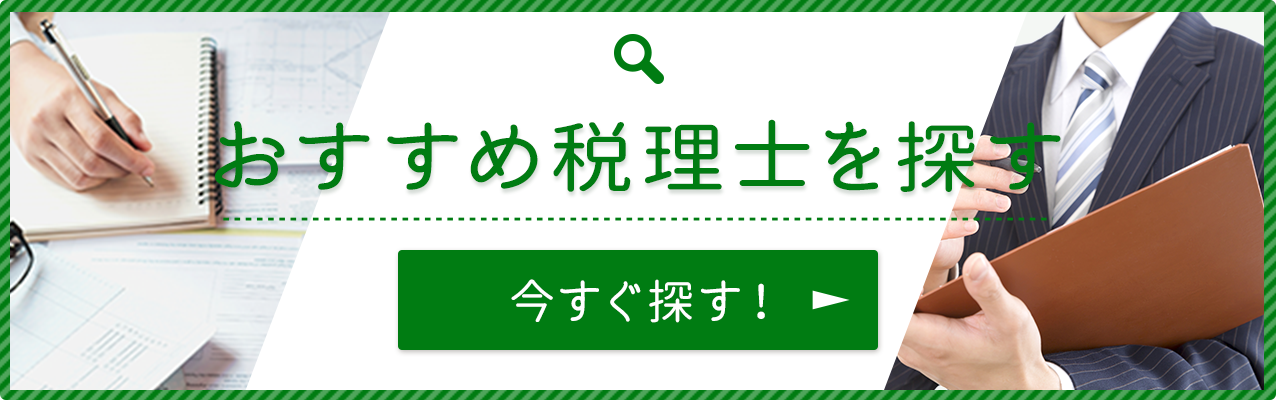相続税を税理士に依頼する際の流れと知っておくべきこと

良い税理士との出会いが相続の成功を決めると言っても過言ではありません。よく準備して良い税理士を探し、依頼しましょう。ここでは税理士に相続の依頼をするまでの流れや税理士に依頼する際のポイントを分かりやすく解説しています。
相続税を税理士に依頼するまでの大まかな流れ
1. 相続発生後の確認事項
相続の発生
被相続人が亡くなった日から手続きが開始します。
まず、死亡届を市区町村役場に提出し、戸籍謄本を取得します。
相続人の確定
戸籍謄本を元に法定相続人を確定します。
必要に応じて相続関係説明図を作成します。
遺言書の有無の確認
被相続人が遺言書を残している場合、公正証書遺言か自筆証書遺言などの種類を確認します。
自筆証書遺言がある場合、家庭裁判所で検認が必要です。
2. 相続財産の調査
資産の把握
被相続人の所有していた資産を調査します。
- 預貯金
- 不動産
- 株式や有価証券
- 動産(自動車、貴金属など)
- 保険金
借入金や未払金などの負債も含めます。
財産評価
不動産については、路線価や固定資産税評価額などを元に評価額を計算します。
現金や預金、株式は時価を基に評価します。
3. 相続税申告が必要かどうかの判断
基礎控除額を確認
| 基礎控除額は以下の計算式 |
|---|
| 基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税申告が必要です。
申告が不要な場合
相続税がかからない場合でも、財産分割や名義変更などの手続きが必要です。
4. 税理士への依頼準備
資料の整理
以下の書類を用意します:
- 戸籍謄本
- 遺言書(ある場合)
- 財産を証明する資料(不動産登記簿謄本、預金通帳の写しなど)
- 被相続人の所得税の確定申告書(必要に応じて)
- 債務を証明する資料(借入金の明細など)
- 各種評価額が分かる資料
税理士選び
地元で信頼できる税理士事務所や相続税に強い専門家を選びます。
面談を通じて、相談のしやすさや費用を確認します。
5. 税理士との契約と申告準備
初回相談
税理士と面談し、財産内容や相続の状況を共有します。
依頼する範囲や報酬について話し合い、見積書を確認します。
契約の締結
契約書を締結し、正式に依頼を開始します。
申告書作成と申告
税理士が相続税申告書を作成し、申告期限内(相続発生から10か月以内)に提出します。
6. 税理士依頼後の手続き
税金の納付
税理士の指示に従い、相続税を納付します。
納税方法は一括納付が原則ですが、分割納付(延納)や物納が認められる場合もあります。
名義変更
不動産や金融資産の名義変更手続きが必要です。
税理士が司法書士などの専門家を紹介する場合もあります。
税理士に相続税申告の依頼をするまでの事前準備
税理士に相続税申告を依頼前に準備をを整えることで、スムーズに相談を進め、申告作業を効率的に進めることができます。
1. 相続の基本情報の整理
戸籍の収集と相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定します。
相続関係説明図を作成すると、相続人の関係性が明確になります。
遺言書の確認
被相続人が遺言書を残しているか確認します。
自筆証書遺言が見つかった場合は家庭裁判所で検認手続きを行います。
2. 財産目録の作成
資産の把握
被相続人が所有していた資産をリストアップします。
- 不動産(土地・建物)
- 預貯金(通帳、残高証明書)
- 株式や投資信託(証券会社の明細書)
- 車両(車検証)
- 貴金属や骨董品
負債の把握
被相続人が抱えていた借入金や未払金などを確認します。
- 借入金明細書
- 未払の医療費や公共料金の請求書
生命保険や年金の確認
生命保険の受取金額や、公的年金の未支給額を確認します。
生命保険金は「非課税限度額」があるため、詳細を整理しておきます。
3. 各種評価額の確認
不動産の評価
固定資産税評価証明書や路線価図を用意します。
必要に応じて不動産の登記事項証明書を取得します。
金融資産の評価
預金通帳の写しや、株式の評価額を確認します。
株式の場合は、相続開始日の終値が基準となります。
動産やその他資産の評価
車や貴金属などの市場価値を確認します。
4. 税理士選びのための情報収集
相続税に強い税理士を探す
過去の実績や評判を確認し、相続税専門の税理士に絞ります。
地元の税理士事務所や紹介サービスを活用すると良いでしょう。
相談時の準備
初回相談時に説明するため、財産目録や相続関係図を簡易的に作成しておきます。
不明点や不安点を整理し、質問リストを用意します。
5. 必要書類の収集
以下は税理士に依頼する際に必要となる主な書類です。
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 被相続人の出生から死亡までのものと相続人全員の戸籍謄本 |
| 遺言書 | あれば家庭裁判所で検認したもの |
| 不動産の固定資産税評価証明書 | 市区町村役場で取得 |
| 登記事項証明書 | 法務局で取得 |
| 預貯金残高証明書 | 銀行や証券会社で取得 |
| 借入金明細書 | 金融機関から発行されたもの |
| 生命保険契約の書類 | 保険会社からの契約内容や受取金額が記載された書類 |
| 公共料金や医療費の明細書 | 未払い分がある場合 |
6. 相続税申告に必要な判断の準備
財産の分割方法を検討
相続税申告時に分割が確定していないと、特例が適用できない場合があります。
遺産分割協議書の作成を視野に入れ、相続人全員で話し合いを進めます。
特例や控除の確認
小規模宅地等の特例や配偶者控除など、適用可能な控除の確認を税理士と相談します。
7. 申告期限の意識
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日から 10か月以内 です。この期限内に申告と納税を済ませる必要があるため、早めの準備が重要です。
相続の依頼をする税理士を探す
事前準備ができたら税理士を探しましょう。税理士を探す際に参考するのは①税理士事務所の立地、②報酬額、③相続実績などです。
相続を依頼する税理士事務所の立地を確認
相続税申告までの間、相続の相談や資料の提出、受取などで何度か税理士事務所に足を運ぶ必要があります。あまり遠すぎず足を運べる距離の税理士事務所をお勧めします。
相続申告の報酬額を税理士事務所のホームページで確認
税理士事務所のホームページに相続税の報酬額を掲載している事務所もありますので(相続財産○○○以上の場合報酬△△△のような形で)報酬額も確認しておきましょう。「初回相談~分まで無料」という税理士事務所もあります。
税理士の相続申告の実績
相続実績件数がホームページに掲載されているようであれば確認しておきましょう。ひとくくりに税理士と言っても法人税、所得税、贈与税、補助金業務などれぞれの税理士によって強みが異なります。「相続」の申告実績件数を確認しておきましょう。
相性の良い税理士に依頼しましょう
立地や報酬、実績などの上記の条件はとても重要ですが、相続申告や納税までの手続きは半年から1年に及びます。調査も含めるとそれ以上の期間となることも少なくありません。それだけ長く付き合う税理士ですから時間をかけ「相性の良い」税理士を探しましょう。
税理士に相続税の依頼をするタイミング
税理士に相続の依頼をするのはどのタイミングが一番良いのでしょうか?それぞれの状況によっても異なりますがいくつかの税理士に依頼するタイミングの例をご紹介します。
相続発生前に税理士に依頼する
相続発生前(亡くなる前)から税理士に相談し始めることも出来ます。この場合は「相続税対策」という段階での相談ですので時間をかけての「節税」という観点で大きなメリットがあります。
経験豊かな税理士であれば不動産、贈与、保険、法人設立など様々な方法によって節税対策を提案してくれます。
明らかに相続財産が多く相続税が多額になることが分かっている場合、相続発生前に税理士に相談することをお勧めします。
相続発生から2ヶ月以内に税理士に依頼する
相続発生から3ヶ月以内に単純承認、相続放棄、限定承認の選択をしなければなりません。2ヶ月以内に税理士に依頼しておけば承認手続きの段階から相談することができます。
相続発生から3ヶ月以内に税理士に依頼する
被相続人が「確定申告」をしている場合、亡くなられた年の1月1日から亡くなった日までの確定申告をしなければなりません。この申告のことを「準確定申告」と言い、準確定申告は相続発生から4ヶ月以内に提出しなければなりません。 そのため被相続人が生前個人事業主であったなどの理由により確定申告をしていた場合、最低3ヶ月以内には税理士への相談を開始しておきましょう。
遺産分割協議書ができてから税理士に依頼する
相続財産をどのように分割するのかを協議し、司法書士に依頼して不動産を登記、名義変更をしてから税理士に依頼するケースもあります。そのような場合でも相続税の申告自体相続開始から10ヶ月以内という期限があるため、申告期限も加味して早めに依頼を開始しましょう。
※1ヶ月で相続税申告書作成しますという税理士もいますが、資料不備などによるそのあとの調査や修正申告ことも考えると早めの税理士への相談をお勧めします。
相続申告後に税理士に依頼する
実際に相続税申告をした後でも申告額が高すぎた場合、還付請求をすることができます。税理士によっては「還付額の何割」という成功報酬型で報酬額を設定している税理士もいます。税理士に依頼することにより土地の評価方法の部分で納税額を大幅に抑えられるケースがあります。そのような税金の還付が期待できる場合には相続申告をした後でも税理士に依頼することができます。
税理士に電話やメールで面談の依頼をする
相続を依頼したい税理士が決まったら面談予約をしましょう。税理士事務所によっては初回の面談が無料という事務所もあります。予約の際には相談時間によって報酬が発生するかどうかを念のため確認しておきましょう。面談予約はたいてい電話やメールで行います。
面談を依頼する際に税理士に伝えるべきこと
面談を予約する際に最低限伝えるべきことは
- 相続人・被相続人の名前
- 相続開始日
- 面談希望日時
相続財産や相続人の人数についての細かい話は面談の際に直接お伝えする形で大丈夫ですが、相続開始日から逆算して、まず相続申告の期限を確認する必要があるため 電話やメールで面談の予約をする際には「相続開始日」を必ず事前に税理士に伝えておきましょう。
その他気になることがあれば税理士に事前に伝えておく
その他面談に先立って伝えておいた方が良いと思うこと、気になっていることがありましたら事前に伝えておきましょう。(相続人同士でトラブルがある、行方不明の相続人がいる、被相続人の配偶者が認知症で判断能力を欠いている・・・など)
場合によっては税理士ではなく弁護士や司法書士の業務が含まれていることもあります。事前にそれらのことを伝えておくことで面談の際に紹介を受けるなどスムーズに話を進めることができます。
事前に税理士に確認しておいた方が良いこと
- 面談に係る費用
- 初回面談での持ち物
電話やメールで面談の予約をする際には初回の面談でどれくらいの費用がかかるのか確認しておきましょう。初回無料、初回何分まで無料、相談1回につき〇〇円、1時間△△円など税理士事務所により様々な形態があります。
また初回の面談の際に持っていく必要があるものを確認しておきましょう。よく資料が準備されていれば直接会って面談する回数も少なくすることができます。
相続の税理士と初回面談ですること
第一回目の面談の場では以下のようなことを税理士から確認されます。
- 大まかな相続財産の確認
- 相続人の確認
土地、建物に関しては固定資産税の納付書や図面などの資料があると大まかな相続財産の価値を把握できます。可能であれば持参しておきましょう。
現預金・株式などの有価証券・保険金・退職金に関しても事前にできる範囲で情報を集め面談の際に税理士にお伝えしましょう。通帳の入金額からそれらの資産を確認するため相続人の通帳は面談に持参しましょう。
相続税申告までのスケジュールを税理士に確認
多くの場合は税理士から今後のスケジュールの話があるかと思いますが、もしそのような話がなければ今後の申告までのスケジュールを確認しておきましょう。
相続税が発生するかしないかを確認
初回の相談で相続税額がいくらになるか、という話までは聞けないかと思いますが「相続税額が発生するのかどうか」は聞いておきましょう。
相続人が被相続人の配偶者の場合、「配偶者控除」があるため一定の金額までは相続税は発生しません。概算であっても「これくらいであれば税金はかからないな」ということは経験豊かな税理士であれば初回の面談である程度把握できます。
また相続財産が基礎控除を下回る場合はそもそも相続税申告が不要になります。
初回の面談では
- 相続税額が発生するか
- 相続税申告が必要かどうか
を確認しましょう。
税理士に正式依頼する前に報酬を確認
初回の面談で必ず報酬を確認しておきましょう。多くの税理士が相続財産を基準にして報酬額を決定するため「計算をしてみなければ分からない」という回答を受ける場合もあります。しかしこちらが大まかな相続財産を伝えていればある程度の報酬の目安を聞くことができます。
正式に税理士に依頼する際に必要なもの
相続の申告業務を正式に税理士に依頼する際、「委任契約書」という書類に委任者(相続人)の署名、印鑑が必要な場合もありますし、特に押印の必要がない場合もあります。この部分に関しては特に規定があるわけではなく実際はそれぞれの税理士事務所の方針により異なります。(念のため初回の面談の際には印鑑を持参しておくことをお勧めします。)
税理士に正式依頼を伝えるタイミングは?
税理士に正式に相続の申告業務を依頼する場合、初回の面談でその旨を伝えることもできますし、”他の相続人と調整が必要な場合”には後日依頼する旨を伝えるというケースもあります。そういう場合には一度相続人と相談する旨を税理士に伝えましょう。
【まとめ】相続税を税理士に依頼する際の流れと知っておくべきこと
以上相続税を税理士に依頼する際の「流れ」と「知っておくべきこと」について書きました。
税理士へ相続税申告の依頼までの流れ
- メールや電話での初回面談の約束
- 初回面談
- 正式依頼
正式依頼までの流れとして必ずこの3つのステップがありますが、事前に相続財産についてある程度把握していると話がスムーズに進みます。初回面談でも土地や建物に関しての情報(固定資産税の納付書)を持参すると良いでしょう。
税理士への相続税申告の依頼までに知っておくべきこと
税理士に相続税の正式依頼をするまでの事前に①税理士の「相続実績」をホームページなどで確認しておきましょう。また初回面談の際には大まかな相続財産を伝え、相続申告の際の税理士報酬も確認しておきましょう。
※もし報酬に関してきちんとした規定がなく曖昧な場合は逆に言うと「相続の実績があまりない」とも考えられます。
相続税申告は相続人と税理士が二人三脚で臨む期間の長い大切な作業です。時間をかけて良い税理士に依頼しましょう。