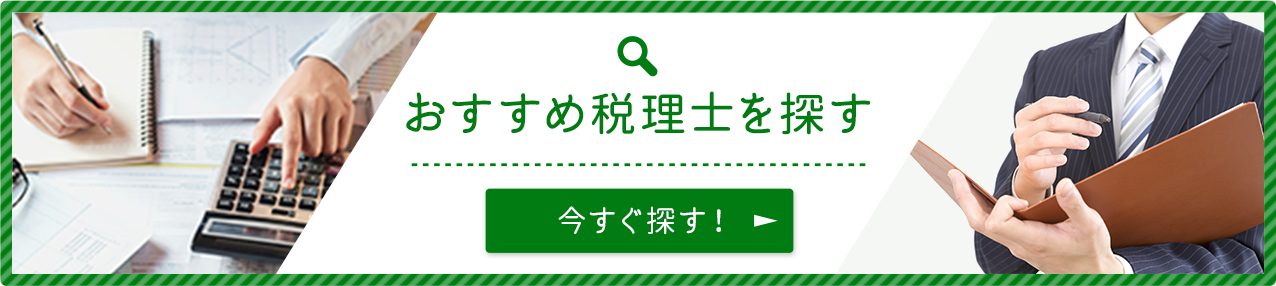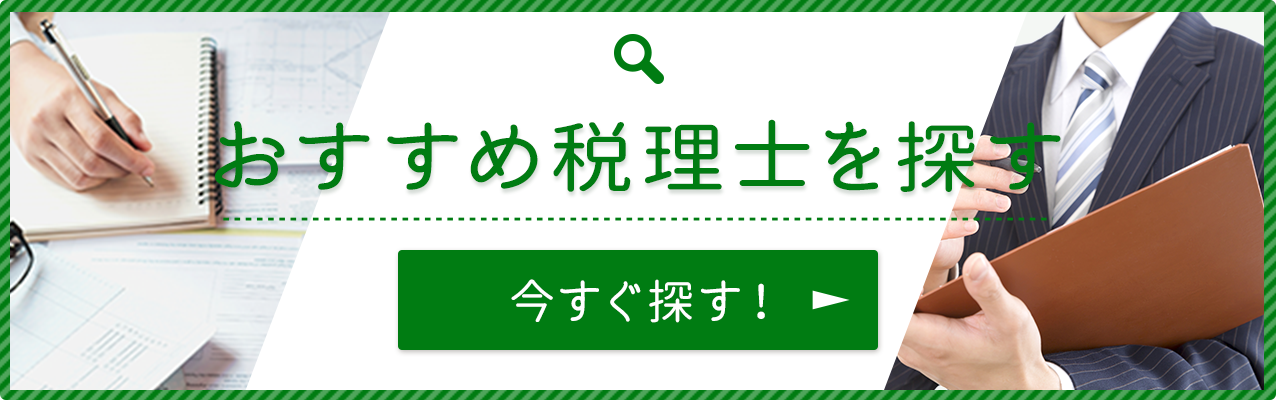遺産分割とは?相続トラブルになりやすい遺産分配の注意ポイントを解説
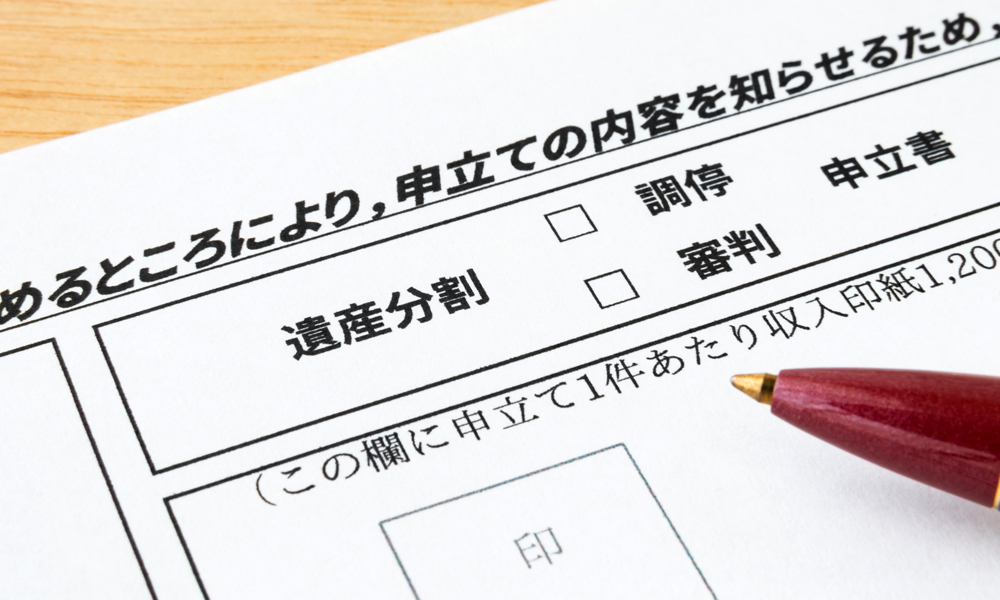
「家族が仲良しだから問題ない」「相続財産が少ないから揉めない」など、自分や家族には遺産相続のトラブルが起こらないと考える方もいるでしょう。ですが、仲の良い家族でも遺産相続で揉めることは多々あります。相続財産が限られているからこそ、トラブルになることもありますから注意しましょう。
遺産分割とは
遺産分割は相続人間で相続財産を分けること
遺産分割とは、相続人が複数人いる場合に遺産を分ける手続きをすることです。相続人が1人の場合、遺産分割手続きは行いません。また、遺言書ですべての相続財産の分配方法が指定されている場合や、事前に決めた分配方法について相続人全員が納得している場合には、あらためて遺産分割協議をする必要はありません。
遺産分割というと、話し合いで解決するイメージもありますが、調停や審判で手続きをするケースもあります。3つの手続きについて見ていきましょう。
遺産分割協議
遺産分割の手続きでは、まずは当事者間での話し合いで解決をはかることになっています。この話し合いを遺産分割協議といいます。基本的には相続人だけで行われますが、専門家などの、第三者が立ち入ることも可能です。
話し合いですから、あとで言った言わない等のトラブルにならないように、協議が成立したら、その内容を遺産分割協議書にまとめておきます。公正証書にしておくと、より確実です。
遺産分割調停
遺産分割協議で話がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に調停または、審判を申し立てます。遺産分割の場合、通常は審判を申してても、まずは調停に付されます。調停は協議と同じく話し合いですが、当事者だけでなく調停委員が間に入って話し合いを進めます。これを遺産分割調停といいます。
遺産分割審判
遺産分割調停でも話がまとまらなければ、裁判という手段もあります。しかし、大抵の場合は、調停で解決しますから、裁判にまで至るのはごくまれなケースです。審判で遺産分割方法を決めるのは、裁判官です。
| 行う順序 | 遺産分割手続き | 遺産分割方法を決める方法 |
|---|---|---|
| 1 | 遺産分割協議 | 相続人間で話し合い(第三者も立ち会える) |
| 2 | 遺産分割調停 | 調停委員立ち会いのもと、相続人間で話し合い |
| 3 | 遺産分割審判 | 判決 |
遺産分割手続きに参加する人
遺産分割手続きに参加するのは、全ての相続人です。また、包括受遺者や相続分の譲渡を受けた人にも参加してもらわなければいけません。1人でも欠けていたことがわかると、遺産分割手続きそのものが無効になってしまいます。
法定相続人
「法定相続人は配偶者と子だから、特に調べる必要はない」と思っていると、後でトラブルになるかもしれません。養子や非嫡出子、妊娠中の子などが存在する場合もありますから、注意しましょう。
法定相続人を確実に判定するためには、被相続人(亡くなった方)の戸籍を出生から調べていきます。
法定相続人が未成年の場合
法定相続人が未成年の場合は、法定代理人が遺産分割手続きに参加します。法定代理人は親権者である両親の場合がほとんどですが、両親も相続人の場合は子と利益が相反してしましまいます。その場合は、家庭裁判所に申し立てをして選任してもらった特別代理人が代わりに遺産分割手続きに参加します。
被相続人の子がまだ胎児の場合は、無事に生まれてから相続権が発生しますから、遺産分割手続きは、出生まで待ってから行います。
包括受遺者
包括受遺者といって、遺言により相続財産の何割かを遺贈するなどとして贈与する財産を明確に指定しない包括受贈を受けた人は、遺産分割手続きに参加しなければいけません。包括受遺者は他人であったり、気まずい関係性の相手というケースもありますが、それでも遺産分割手続きには必ず参加してもらわなければいけません。
遺言で遺贈分を指定された人でも、特定の財産を遺贈される人は遺産分割手続きに参加しません。
相続分の譲渡を受けた人
法定相続人から相続分の譲渡を受けた人は、遺産分割手続きに参加しなければいけません。また、もしも法定相続人がすべての相続分を他の相続人または他人に譲渡した場合は、その法定相続人は遺産分割手続きに参加しなくてもよいことになります。
遺産分割に期限はない
遺産分割手続きに法律で定められた期限はありません。ですが、遺産分割をせずに放っておくと、いつまでも相続ができません。預貯金は引き出せませんし、不動産は売却や活用ができなくなります。
長期間そのままにしておくと、次の相続が発生(法定相続人が死亡すること)してしまい、遺産分割がさらに複雑化してしまうかもしれません。遺産分割手続きは、面倒でも早めに済ませておくことをおすすめします。
遺産分割は専門家へ相談を
遺産分割手続きは、ほとんどの場合、遺産分割協議か、遺産分割調停で行います。万が一相続人だけの話し合いで揉めてしまった場合も、専門家がサポートをすれば話し合いで解決できるということです。
遺産分割手続きは、家族の問題や住んでいる家などの生活に直結することからも、スムーズに進まないと大きなストレスとなります。トラブルを未然に防ぐためにも、弁護士や税理士などの専門家から早めにサポートを受けるといいでしょう。
遺産分割でトラブルになりやすいケース
相続財産が不動産のみというケース
遺産分割のトラブルは、実はごく普通の一般家庭でも頻繁に起こっています。多額の相続財産がなくても、分割しにくい遺産があればトラブルになってしまうのです。
よくあるトラブルに、相続財産が不動産のみ、というケースがあります。相続人が2人以上いる場合、不動産の分割方法で揉めることが考えられます。不動産はその価値をどう考えるかも問題です。あまり価値がないからと、一人の相続人が強引に相続しようとするケースもあり得ます。
売却するか、活用するか、相続人の誰かが住み続けるか、など用途に関しても相続人間で意見の分かれやすいところでしょう。相続人の誰かが居住している不動産ならば、分割することで住んでいる家を失う恐れもあるのです。
兄弟姉妹(子)だけが相続人というケース
配偶者がいない、または既に死亡している場合などで、相続人に複数の子がいるケースも注意が必要です。兄弟姉妹の間では年長者の意見が通りやすいなどの上下関係がある場合も多く、あとに遺恨を残しかねません。
また、被相続人から生活費のサポートを受けていた子の特別受益や、被相続人の介護をしていた子の寄与分をどう考えるか、なども兄弟姉妹間で意見のまとまりにくいところでしょう。
子どもがいないケース
子がいないケースも、実は遺産分割で揉めることがあります。子がいれば配偶者と子だけが法定相続人になるのに対し、子がいないと、被相続人の両親や兄弟、甥や姪までも相続人になる可能性がでてくるためです。
配偶者と被相続人の両親の関係がよくないことも考えられます。両親が他界していている場合、法定相続人は被相続人の兄弟姉妹ですが、配偶者との関係性はどんどん遠くなります。兄弟姉妹が他界していれば甥や姪が代襲相続する可能性もあります。
遺言で遺留分を侵しているケース
全ての相続財産の分配方法を遺言で指定していれば、トラブルが起こらないとは限りません。遺言で指定した割合が遺留分を侵していれば、遺留分減殺請求をされる可能性があるからです。
遺留分減殺請求をされると、せっかく分配が終わった遺産の一部を現金化して支払う必要がでる可能性もあります。
前妻との子や非嫡出子、養子がいるケース
音信不通だった前妻との子や、認知された非嫡出子の存在が相続人調査で初めて明らかになることもあります。法定相続分は前妻との子も、認知された非嫡出子も、養子も同じ割合ですから、長年一緒に暮らしていた子にとっては納得がいかない場合もあるでしょう。
遺産分割をスムーズに行うために
まずは正確な情報を得る
遺産分割で揉めないために、まずは正確な情報を得ましょう。相続人調査や相続財産調査をしっかりと行うことで、あとで知らない相続人が出てきた、相続財産が予想よりも少なかった、多かったなどのトラブルを未然に防げます。
冷静な話し合いが不可欠
遺産分割協議には、相続人全員の参加と同意が必要です。スムーズに話し合いを進め、ストレスを大きくしないために、冷静に話し合いを行いましょう。
お互いの立場を尊重する
相続人それぞれの立場を尊重することで、話し合いはスムーズに進みます。例えば、配偶者は自分の子に多く相続させたいと考えがちですが、婚外子は今まで苦労した分たくさん相続したいと考えるかもしれないのです。そのような場合、お互いが譲らなければ遺産分割協議は進みません。
トラブルにならない遺言作成を
遺留分を侵している遺言や、特定の相続人の心情を害する遺言は、トラブルの元となり得ます。遺言を作成する際は、相続人の心情に配慮し、遺留分を侵していないかなどの確認をしましょう。各相続人に具体的な相続財産を指定して分配しておくと、より効果的でしょう。分配方法を指定しない財産は、なるべく遺さないでおくこともポイントです。
専門家のサポートを受ける
遺産分割手続きでトラブルにならないためには、専門家のサポートを受けるのが一番よいでしょう。正確な情報を得て、客観的な意見を取り入れることで感情的な話し合いではなく、実務的な話し合いができるでしょう。
遺産分割は税理士に相談を
遺産分割で困ったら、まずは専門家へ相談しましょう。トラブルを未然に防ぐためにも、精神的なストレスを軽減するためにも、第三者である専門家は心強い味方です。税理士などの専門家なら、相続税の負担も考慮して、適切なアドバイスができるでしょう。